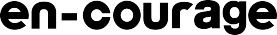|

|
◆東北大学の大学院でエネルギー系の研究をしている理系院生の阿部さん。 就活中、文系の女子学部生2人と一緒になった集団面接で、泣くほど悔しい思いをしたという阿部さんの就活とはどのようなものだったのでしょうか? 理系院生の就活に迫ります。
思考停止の院進学
−阿部さんは理系の大学院生ということですが、就活を始めた経緯を教えてください。
阿部:本格的に就活を始めたのは、M1の5月です。
研究室の先輩が早期に内定を貰っている様子を見て、自分はその先輩と比較して劣っているから、就活も苦労しそうだなと感じていました。
また、夏から秋にかけて放射光施設出張や学会発表、論文投稿が予定されており、研究が忙しくなるのもある程度分かっていたので、早めに就活を始めることにしました。
就活序盤(M1の5〜8月頃)は、今の自分が学んでいる分野とは全く関係のない業界・企業を見てみようと思い、人材系や金融系の企業のインターンに参加しました。
−”理系の大学院生”となると自分が大学院で研究している分野をメインに就活をするというイメージがあります。阿部さんはなぜ、関係のない業界・企業を見てみようと思ったのでしょうか?
阿部:大学院進学という意思決定プロセスに対し、後悔していたことが強く影響しています。
学部生時代に、あまり深く考えずに大学院進学を選択しました。
これは、「理系の自分は大学院に進学するのが当たり前だ」という固定観念に縛られたまま、疑問を持つことなく大学院進学を選択していたからです。
就活をするか否かは、選択肢に入ってすらいませんでした。
そのことをずっと後悔していたので、就活では「この業界は自分には合わない」という固定観念に縛られて後悔したくないという思いがありました。
ですので、理系院生の自分には関わりがなさそうな文系業界、中でもあまり興味を持ったことのなかった金融系や人材系の企業を見てみることにしました。
理系院生は、研究している分野に進むことが大多数であると感じていたので、一般論ではなく、自分の目で見たうえで「この業界、思っているのと違った」というような気づきが得られれば嬉しいなと思っていました。

自分のことなのに、わからない
−早期から就活を始めていたとのことで、無双しそうなイメージがありますが、何か壁に当たったことはありましたか?
阿部:3月に選考が本格化する前に選考練習をしておこうと思って参加したITベンチャー企業の集団面接でコテンパンにされたことです。就活解禁直前の大事な時期に、今までの積み重ねが崩れ落ちた思いがしました。
面接では、志望動機や学生時代頑張ったことなどのエピソードに対して「なんで?」「どうして?」と深掘りされます。もちろん、その企業の面接でもそうだったのですが、その企業の面接での深堀はとりわけ深く鋭く、自分は途中で答えに詰まってしまいました。
確かに、本命ではない企業だったので、確固たる志望動機があったわけではありません。
それでも、それまで受けた他の企業の面接ではある程度の誤魔化しが効いていました。
しかしながら、このITベンチャー企業の面接では、学生時代頑張ったことや自己PRなど初歩的な質問でさえも、度重なる鋭い深堀りに対しては、浅い答えしか出せませんでした。
しかも、その集団面接で一緒だった文系の女子学部生2人は、その深掘り質問に対して筋の通った答えを堂々と話しており、その2人と自分との差を見せつけられ、愕然としました。
ある程度、早めに就活を始めたことでやりたいことも明確になっているはずだし、自分のこともよく把握できているつもりだと考えていたので、いかに自分自身の理解が足りないのか痛感しました。
就活解禁前の試金石として臨んだ選考で、一気に自信が無くなりました。
この時ばかりは涙がこぼれましたね。
この時、初めて「自己分析」の重要性を感じました。
−では、その後の就活はどのように進めたのでしょうか?
阿部:自己分析を最初からやり直しました。
正直、それまで自己分析はできていると勘違いしていたんですよね。
でも、面接で何度も深堀されたことで、実は浅い部分しか出来ていなかったことに気付きました。
そのためにまず、自己分析が出来ているという勘違いがどうして起こったのかを考えました。
その結果、自己分析をアウトプットする場をあまり設けていなかったこと、そして質の高いフィードバックを受ける機会も少なかったということに気づきました。
自己分析は、自分だけで考えればある程度の答えが出ると思っていたのですが、どうしても限界があります。アウトプットしなければそれを客観評価できないため、限界を認識すること無く、満足してしまいます。
自分では納得して、これ以上無いと思っている考えでも、他者から別の角度で切り込まれると脆さが露呈するというようなことが往々にしてあります。
だからこそ、自分以外の他者にアウトプットをして、客観的な視点で意見を受けること=フィードバックが重要であると気づきましたね。

自己分析は、1人ではできない
−アウトプットとフィードバックを意識してから何か変化はありましたか?
阿部:自分にとって大切な価値観や軸が明確になり、自信を持って面接に臨めるようになりました。
それまでは企業に合わせて自分を変えるスタンスで面接を受けていましたが、「自分がどんな人間であるか」を言語化し、納得されるように説明できるようになったので、自分がその企業に合っているのか確かめるスタンスで受けるようになりました。
また、改めて自己分析を進めていく中で、今まで無意識にしていた意思決定でも、意外と筋が通ってたんだなということにも気づきましたね。
自分の場合は、東日本大震災の経験が価値観に大きく影響していて、大学院では地学系の専門分野に携わっていることや、就活もなんだかんだ「エネルギーインフラ系に携わりたい」という選択に帰結したのは、それが影響していたのだと気づきました。
無意識にしていた意思決定の共通項を見つけ出し言語化する作業、それも自己分析だと思います。
−最後に、就活中の19卒の学生のみなさんに向けて一言いただければと思います!
阿部:とことん、自分と向き合ってほしいですね。
つまり、自己分析ということなのですが、「なんでだろう?」「どうしてだろう?」を繰り返して、本当に自分が望んでいることを見つけてほしいです。
もちろん、人との出会いも大切です。
自分もそうでしたが、理系の大学院生の就活は、あまり深く考えずに「研究を活かせるところに行こう。行かなければならない」という固定観念に囚われがちです。
だからこそ、色々な人と出会い、様々な考え方や価値観に触れながら、自己分析を深めていってほしいです。自己分析は、1人ではできません。
自分は、エンカレッジのメンターとの個別面談の中で、アウトプットしてフィードバックを受けるというサイクルを繰り返しました。
そのおかげで、かなり自己分析が進んだので、本当に助かったなと思っています。