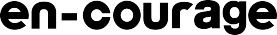|

|
◆面接を進めていると、稀に聞かれる「最後に一言はありますか?」という質問。あなたならどう答えますか?その形式が急に変わった「フリー回答」という点から結構戸惑うという方も多いはず。今回は実際に面接官として活躍する田宮さん(仮名)にその意図も聞いてみました。
面接の最後に一言は誰が聞いてるかを判断せよ
– 田宮さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
田宮さん(以下、田宮):よろしくお願いします。
– 面接で企業から聞かれる「最後に一言は?」という質問の真意について、読者の学生さんたちも気になっているのではないかと思います。さっそくですが、その採用側の意図をお聞きしてもよろしいでしょうか。
田宮:了解しました。
まず、この質問に回答する前に、一つ覚えておいて欲しい前提があります。
それは、面接における質問者の採用権限によって、同じ質問でも意図が異なるということです。
なぜなら、企業が行う面接というのは、篩(ふるい)に掛ける選考とその人を採用するかどうかを決める選考との2種類あるからです。
具体的にいうと、就活において、ほぼ最終選考以外の面接に出てくる企業の面接官は、その応募者を採用するという意思決定権を持っておらず、次に通して良いか否かをジャッジしているに過ぎません。
逆に最終選考に出てくるのは、役員クラスや社長だったりしますよね?
彼らにしか企業の採用の意思決定権は存在し得ないのです。
だからこそ、種類が違う面接として、それぞれ「最後に一言」における質問の意図は異なると言えます。

面接の「最後に一言」にはどんな意図があるのか
田宮:さて、この前提を踏まえた上で、面接における「最後に一言」を質問する意図についてご説明していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・採用権限がない面接者の場合の質問意図
①個人的にはいいと思ってるが、上長へのPUSHポイントが少なくこの一言で後押ししてあげたい。
②合否判定に相当困っており、最後の一言の出方もジャッジポイントにしたい。
③不採用決定者であっても、とりあえず聞いてあげるかという就活生への面接満足度を上げたい。
・採用権限ある役員/社長の場合の質問意図
①質問への回答力や逆質問力を見ている。
②入社への本気度(熱意)を感じたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず、「採用権限がない面接者の場合の質問意図」を解説します。
まずは、「個人的にはいいと思ってるが、上長へのPUSHポイントが少なくこの一言で後押ししてあげたい。」というケースです。
面接官は、自分の介在価値を次回の面接担当者にヒットする量と率を指標に評価をされます。
いわば、自分がフィルター役として機能できているということを、上位レイヤーの面接官にアピールと提案をしなければなりません。
だからこそ、なぜこの候補者を合格にしたのかの理由が欲しいのです。
それを面接時に、良いとは思っているが、言語化するほど推薦理由を持てていない時に、「最後に一言」を求めます。
次に、「合否判定に相当困っており、最後の一言の出方もジャッジポイントにしたい。」というケースです。
先ほどのものと比較すると、合格が決まっていないということが大きな違いとして挙げられます。
ここで足りない要素を挙げるならキリがないし、どれを足りないと面接官が感じているのかを候補者は正直わからないと思います。
ただ、共通した面接官の悩みが一つあります。
それは、合格レベルの候補者を不合格にしてしまう恐れです。
そのため、このケースでは、面接官が合格を出す上での物足りないと感じている要素をはっきりとわかっていない限りは、「最後に一言」で熱意をアピールすべきかと思っています。
面接官は熱意があり、判断を迷うくらいならもう一度チャンスを挙げた方がいいなと思うからです。
そして、「不採用決定者であっても、とりあえず聞いてあげるかという就活生への面接満足度を上げたい。」というケースをご紹介します。
企業は、不採用の候補者であっても、心象を悪くして欲しくないと考えています。
そのため、その企業との面接が有意義であったと少しでも感じてもらうために、話したかったことを質問されなかった後悔のないように「最後の一言」を聞いている形になります。
候補者からすると、こうなっている時に為すすべはありませんが、次回の面接に役立てると思って、盗める情報があれば盗んでいってもらえればと思います。
今度は、「採用権限ある役員/社長の場合」の質問意図についてお話しして行きます。
まずは、最後に一言で「質問への回答力や逆質問力を見ている。」というケースです。
今までは、補填の意味が強かった「最後に一言はありますか?」という質問ですが、今度はダイレクトに選考の色が強いものになっています。
理由は明白ですが、最終面接なので、企業として採用するかしないかを決定しなければならないからです。
具体的に候補者はどうすれば良いかと言うと、企業への関心をアピールするため、逆質問をし、「対話」意識すると良いと思っています。
最後に一言は基本的に自由な設問なので、これまで聞けなかった疑問や経営者だからこそ分かる企業の方針や考えなど、率直に自分が入社する企業としての関心に対する質問から入っていくと、対話が生まれます。
意味のある質問が続くと、「逆質問力がある」と、意思決定者は深掘りのセンスを感じることができます。
だからこそ、関心ごとをトピックとして、対話を意識すると良い結果が生まれると思います。
さて、最後に、「入社への本気度(熱意)を感じたい。」というケースです。
結論から言うと、コミュニケーションは先ほどと同様で問題ないです。
逆質問と対話により、熱意を伝えて行きます。
ただし、ここで重要なのは、「自分ごととして質問をしている」と意思決定者に伝わっているかということです。
つまり、どういうことかというと、「質問をした回答に対する反応が前のめり」ではないと熱意が伝わりません。
具体的には、企業の採用の意思決定者が質問に回答した返答に、
・自分の解釈をぶつけているか
・入社した後のことを前提として、そのディスカッションができているか
・良い回答を得られた上で、入社意思をダイレクトに伝えられているか
などが挙げられるかと思います。
– 田宮さん、非常に理解ができました。面接で「最後に一言」を聞かれた場合は、自由な回答に見えて、実はすべき回答として意図に沿うことが重要であることも理解できたと思います。

面接の最後に一言のポイントまとめ
インタビューの内容より面接の最後に一言について考えていくポイントを最後にまとめます。
「最後に一言」を対策するポイント①
面接選考は、2種類あり、採用権限のあるなしで質問の意図が変わり回答すべき点が違う。
「最後に一言」を対策するポイント②
採用権限のない面接官との面接では、熱意を持ってアピールせよ。
「最後に一言」を対策するポイント③
採用権限のある面接官との面接では、逆質問で関心をアピールせよ。
以上です。
最後の一言の回答をうまく活用して、就活を成功に導いていただければと思います。