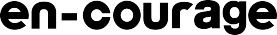|

|
◆就職活動の中で、幾度も耳にする「優秀な学生」という言葉。そう呼ばれる人々は、難関だと言われる企業からの内定を複数獲得することも多いです。 彼らに共通する特徴とは一体何なのでしょうか。今回は、筆者の留学経験から「リーダーシップへの考え方」について紹介します。
リーダーとボスの違いとは。

上記の図は、アメリカのウェブサイトから話題になった、ボスとリーダーの違いを示した図です。この図は、筆者が実際に留学を通して感じた「日本と海外のリーダーシップ」の違いを端的に示しています。
高度成長期期の日本では、自動車産業などが自社の成長にとって都合のいい労働者を確保するために、工場での生産性が高い「マニュアル型人間」を学校の詰込み型教育を通して大量に生産してきました。それが功を奏した影響の反動としてなのか、日本でのリーダーは上の図でいう、ボスのような人のことだと思われがちです。
しかし、留学中の様々なコミュニティーで活躍している人は「ボス」ではなく、自分のフォロワーたちを束ね、かつその先頭を走れる上の図でいう、「リーダー」でした。日本でも近年では上記のような考え方に改善が見られ、就職活動でもそのような「リーダー」が求められていると強く感じました。
優秀だという評価を受ける人の中には、このような「リーダー」の経験をしている人が数多く見受けられました。そういうと「私はリーダーの経験なんてない…」と悲観的になる読者もいることでしょう。
もちろんリーダーの経験も大事ですが、それと同じくらい「フォロワーになったときの在り方」が大事になります。
大事なのは当事者意識をもつこと
自分がリーダーではなく、フォロワーになるとき、「リーダーがやってくれるから」とか「私がやらなくても、他のメンバーがやってくれるさ」と考えてしまうことはありませんか。
この現象は「働き蜂の法則」というのもので説明できます。この法則は1つのコミュニティーにおいて、よく働く蜂と、普通に働く蜂と、働きの悪い蜂の3種類の蜂がおおよそ2:6:2の割合で分かれるという法則です。これが、リーダーとフォロワーのコミュニティー内でも起きてしまうのです。
例えば、「自分がリーダーになると、これまで一緒に頑張ってきたライバルや、仲間たちのモチベーションやパフォーマンスが落ちてしまった…」
「周りのメンバーが口は出すものの、誰もアイディアなどを実行に移そうとしない…」
やる気を出して結果を出す。これは非常に素晴らしいことですが、それによって同コミュニティーの誰かが「怠け蜂」になってしまうのは組織としては損失なわけです。
自分がうまくいっている時、それが組織の利益になっている時は、当事者意識が高く、リーダーシップを発揮することができます。しかし、重要なポイントは自分が「フォロワー」側になり、「怠け蜂」になってしまいそうな時なのです。
要するに、自分が「ボス」や「怠け蜂」になりそうになった時に、自分が「そのコミュニティー内のどの部分」でバリューを出せそうか客観的に見極めて、強みを発揮する。優秀な人は、この意識で自然と行動が出来ています。これを読んだ皆さんは、当事者意識をもって、リーダ-シップを発揮してくださいね。