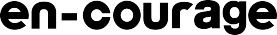|

|
◆就活シーンで必ず誰もが通る面接への不安。うまくいったという感覚があっても落ちたり、落ちたなと思ったら受かったり。就活での面接は自分で振り返ってもどこを改善したら良いのかがわかりにくいです。そもそも面接官は何を見ているのだろうという疑問から、面接練習のコツまで、本記事で解説していきます。
就活に重要視される面接
就活には、エントリーシート、グループディスカッション、面接など、様々な選考プロセスはあれど、内定取得までにほとんどの企業が取り入れているのが、面接です。
なぜ就活シーンでの面接は他の選考プロセスとは違い、ほとんどの企業が取り入れるのでしょうか。
それは、「ひととなり」を見極める上で、これ以上の方法が現時点ではこれ以上にない手法だからです。
新卒採用は、ポテンシャル採用です。そのため、企業はスキルや経験以上に、「人間性」と「自社企業」のマッチングを重視をしています。
就活は面接からが本番と言っても過言ではありません。とはいえ、面接官は全ての応募者との面接を行うには限界があり、エントリーシートやグループディスカッションは、面接を行える限界数に応募者を制限するためにあると言えます。
だからこそ、企業における採用プロセスの中で面接は非常に重要な位置付けとされ、ほぼ全ての企業が取り入れているのです。
ただ、面接は企業によって、一様のことを言っても合否が変わります。
今まで合否に正解があった学生生活とは全く違う世界観に突入するからこそ、困惑をします。
面接練習はどのようにしたら良いのか、自分一人で練習しようにもわからなくて当然です。
まずは、そもそも面接は何があると合格になるのか、これを知り、面接練習を始めていきましょう。

面接官は何を見ているのか
結論からいうと、面接は相手(企業・面接官)が何を求めているかが分かり、自分がそれを提供することができれば、合格することが可能です。
多くの場合、前提である「企業や面接官が求めていること」が分からず、いくら面接練習を行っても上達しないという状態に陥っています。
そのため、企業や面接官は何を求めているのかを解説していきます。
就活での面接シーンにおいて、企業が求めているものは、「ほとんどの企業が共通して求めていること」と「企業によって個別に求めていること」の2つが存在しています。
さらに「ほとんどの企業が共通して求めていること」はレベルが2つに別れ、さらにその上に「企業によって個別に求めていること」という3ステップになっています。
このステップ別に面接官が求めていることをクリアするように、練習をしていけば面接を上達することができます。
実は、このステップ順と企業の選考プロセスが進むステップは酷似しています。
就活の際に、2次選考まではいくけれども、その次になかなか進めないという方は、ステップの内、どこでつまづいているのかをチェックしてください。

ステップごとの効果的な面接練習
では、さっそくそのステップと面接練習の方法について説明をしていきます。
面接練習ステップ1:欠陥がないか
面接練習ステップ2:基礎能力を備えているか
面接練習ステップ3:マッチしているか
【共通して求められること】
面接練習ステップ1:欠陥がないか
最初に誤解のないように釈明すると、その職務を遂行するにあたっての欠陥がないかの見極めになります。
たとえ不合格だとしても面接官がみなさんの人間性を否定した目で見ていたという訳ではありません。
ここでは一旦総合職を例に、解説をしていきます。
企業は多くの場合、面接を複数回選考プロセスに取り入れています。
そのため、最初の面接では、この点を見られていることは必至です。
初期フェーズで見ている「欠陥」とは、具体的には以下の3つが挙げられます。
[面接で見られる欠陥①]印象が悪くないか
総合職、もっと言えば、クリエーターではない、ビジネスマンという領域に属する人たちは、対人を通した仕事を行います。
そのため、面接官は、皆さんの対人に立った際の印象を見ています。
極端に言えば、人に「不快感を与える印象要素を持っていないか」です。
身だしなみは当たり前のこと、よくやってしまいがちなのは、「コミュニケーションによる悪印象」です。
つまり、ここですべき面接練習は、自分が「攻撃的であったり、否定、悲観的なコミュニケーションを取ってしまっていないか」をチェックすることです。
一番良い面接の練習方法は、初対面の人と30分話した結果の印象とその変化を聞くことです。
ただ、なかなか初対面の人に印象を聞く、というのはハードルが高い行為です。
ここでとっておきの方法として、大学のキャリアセンターが行う面接練習会を活用したり、初対面の人が複数集まる就活の面接セミナー等を活用していくことをオススメ例として挙げておきます。
[面接で見られる欠陥②]志望する姿勢はあるのか
このフェーズで面接官は、仮に第一志望じゃなくとも、本当に志望する姿勢はあるのかを見ています。
面接官からすると、志望する気が一切ない学生は、正直単なる冷やかしに過ぎません。
これも当たり前のことのようでよくやりがちな落とし穴が隠されています。
それは、企業を選ぶ時の軸を教えてくださいという質問です。
この質問において、自分の軸の延長線上にその企業を置かない人はそういないと思います。
ただし、この回答の精度によって、どれだけ本気で考えているのかが測れてしまうということに落とし穴があるのです。
例えば、ある商社の面接官にこの質問をされたとします。
その際に、軸は、「スケールの大きいことができるかどうか」と答えた人と、「事業開発を前提にいかに大きなことができるか」と答えた人がいた場合に、どちらの方が商社としてのこの企業を志望しているかが伝わってくるでしょうか。
このように、単に志望軸としての延長線上にその企業があるかだけでなく、その企業やそれを取り巻く環境を研究したり、そこに自分自身がいかにリンクしているのかをちゃんとアピールできているのか、という観点については面接練習でチェックが必要です。
ここの練習方法は、想定企業を設定した模擬面接が有効です。
さらには、一つの企業ではなく、複数の企業のケースを想定し、就活における軸をその企業ごとに翻訳していく練習をすることができればより大きな効果が望めます。
[面接で見られる欠陥③]人の話が聞けるか
次の面接のステップに繋がるチェックポイントです。
ここでは姿勢と応答能力が見られています。
姿勢に関しては、「人の目を見て話を聞いているか」「然るべきところでメモを取っているか」「相槌を打ち、話し手である面接官=自分を不快にさせないか」など、話を聞く上での皆さんの行動から面接官が姿勢を読み取っています。
練習方法は、面接練習の際に、練習相手にこのチェックポイントを伝えて、フィードバックをもらうことが重要です。
なぜなら、無意識の行動がNG行動になっているケースが多いためです。
これに関しては、指摘されたポイントを、意識的に練習し、取り組むことによって改善を図る他ありません。
次に、応答能力です。
ほとんどの方が、このポイントでつまづきます。
ビジネス敬語を話すという不慣れな環境がよりこの応答能力を著しく下げることにも繋がります。
応答能力で見られているポイントは、質問に対して端的に答えられているかのみです。
これはご自身でチェックと練習を繰り返すことができるはずです。
具体的な練習方法は、普段の会話の中から、質問を投げられた際に、テンポを気にせずじっくり考えた上で、「結論から言うと〜」と枕言葉をつけて見ましょう。
そうすると自然に、端的に回答するチカラが身につくはずです。
面接練習ステップ2:基礎能力を備えているか
このステップでは、足切りとしての面接や質問をクリアし、求める能力の水準値を満たしているのかを見られているフェーズです。
多くの企業に普遍的に求められているスキルが2つがあります。
それは、地頭とコミュニケーション能力です。
細かい要素としての定義や強度は違えど、就活での面接シーンにおいて面接官に見られているポイントは一様です。
こちらにおいて解説をしていきます。
「地頭」と「コミュニケーション能力」は、同じポイントで見られていることが多いので、一つの練習法をご紹介します。
それは先ほどのステップにおいて、応答能力についてご説明をしましたが、この延長線上にあるのが、ここでの能力になります。
面接で行われる質問に端的に答えられるチカラに加えて、「ズレがないか」を見られています。
文面に起こした際に、論理的な整合性があるコミュニケーションが取れているかと言い換えた方がわかりやすいかもしれません。
具体的に言うと、なぜ(why)で質問されているのに、理由を答えておらず事象を答えていないか。などが挙げられます。
例:(質問)なぜ弊社に応募されたのですか?(答え)私の実家の家業との関わりがきっかけでした。
文面で見ると、違和感を感じませんか?
なぜと理由を聞かれているにも関わらず、応募した背景を回答してしまっています。
このケースおいては、家業で起きた何らかの事象が〇〇の理由を引き起こしたということが伺えますが、面接官が聞きたいのは、この〇〇に当てはまる理由についてのはずです。
その理由が起こされた背景を質問をしてはいないため、答えにはなっていないのです。
残念ながら、面接シーンにおいてはこの回答ズレに関しては日常茶飯事です。
面接練習をしていくコツは、質問の5W1Hを毎度確認することです。
もし、質問の中に5W1Hが確認をすることができなければ、面接官に今の質問は、「なぜ〇〇したのかと言う理解でよろしいですか?」と逆質問をしましょう。
【面接で個別に求められること】
面接練習ステップ3:マッチしているか
これまでの面接で能力要件における合格基準を満たしたこととなります。
就活シーンでも選考プロセスの後半の面接で見られているポイントが「自社に合うか」です。
自分という人物像が企業にぴったり合うことを面接官にアピールしていく必要があります。
面接練習をしていくポイントは、その企業の持つ価値観を抑えることです。
価値観における情報の仕入れ方は様々あります。ネット検索でもOB訪問でも取得することができます。
更に言えば、就活フェーズの初期の面接で面接官に質問をすることも有効です。
価値観を取得できたら、自分の価値観とリンクさせられる部分を探します。
自分とリンクさせられる部分を見つけられたら、それを自己PRに落とし込めるように面接練習を繰り返します。
いかがでしょうか。様々な面接練習のコツをご紹介していきましたが、ご自分だけで実施できるものは少ないです。
ぜひ練習の場に足を運んで、実践してみてください。