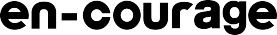|

|
就活の基礎 業界研究の気になるあれこれ
業界研究といえば、キャリアを考える上で、基礎的、かつとても重要なもの。
そんな業界研究についての目的や、いつからやるのが良いのか、どんな方法でやるのがよいのかなど、就活生が気になるあれこれをまとめました。
業界研究は何のため?まずは目的の説明
そろそろサマーインターンも始まり、就活も本格化しているころ。就活において、自己分析と並んでよく聞くことの多い業界研究ですが、何のために行うのでしょうか。
まずは目的を整理していきます。そもそも、業界研究は何のために行うのかというと、大きく以下の2つです。
- 自分にあった、業界や企業を見極めるため
- 選考において、志望動機などをまとめるため
いつからやる?業界研究を始めるタイミング
業界研究は、どのタイミングで行うのでしょうか?
基本的には必要性を感じたタイミングで行うべきなのですが、大きくは2つのタイミングで始めることが多いようです。
- 志望業界を絞っていくとき
- エントリーシートや面接などの選考前
1.志望業界を絞るとき
就活を始めて、まず気になるのはどんなことを、どんな流れで進めるのかということではないでしょうか?
就活生がやることは大きく、以下の3つです。
- 自分のことを理解する自己分析
- 入社する企業を決めるための業界研究、企業研究
- エントリーや面接など、実際の選考活動
自己分析を行うことでキャリアにおいて大切にしたいことや、求めることなどを明らかにしたうえで、就活を進めることができます。
次に自己分析で明らかになったことをどんな企業や業界であれば実現できるのかを、次に考えていく必要があります。
2.エントリーシートや面接などの選考前
就活が進むと、実際の企業選考を受けていくことになります。
この段階では、自分のことはもちろん、選考を受けている業界や企業についての理解が求められるようになります。
採用担当者は、就活生の業界や、企業についての理解を確認することで、目の前の就活生がどの程度、熱意を持って選考を受けているのかを知ることができます。
さらに、就活生の情報感度や、分析力なども把握することができます。
選考においては、どの企業も自社に合った学生を採用したいと考えています。しかも、最近では売り手市場と言われ、新卒採用に苦労する企業が増えており、採用担当者は、より多くの学生に自社へ興味を持ってもらおうとしています。
と、同時に入社する意志のある学生を、見極めようとしています。入社意思を見極めるには、就活生の熱意を見ます。
熱意は、いろいろな行動から分かります。業界研究の深さもその1つです。

どうやって進める?業界研究のおすすめの方法
業界研究の目的と、時期については理解していただけたかと思います。次に実際の業界研究をどのように進めるかについてまとめていきます。
業界研究の進め方において、重要な要素はやはり情報源です。業界研究で主に使う情報源は、以下のように分類されます。
- 業界研究用にまとまっている書籍
- 業界情報に特化した書籍や新聞
- 企業が出している株主総会資料等
- その業界で働いている社会人
- その業界に内定している先輩
しかしここで上げた情報源それぞれに、メリットとデメリットがあります。なのでそれをまとめていきます。
・業界研究用にまとまっている書籍
【メリット】
-比較的、安価に入手することができるので始めやすい
-いろんな業界が網羅的に載っているので、情報の整理がしやすい。
【デメリット】
-各業界が網羅的に載っているので情報が薄い。
-多くの人が、参考にする情報なので面接などで話すことがある場合に、同じような内容になりやすい。
・業界情報に特化した書籍や新聞
【メリット】
-業界特集などでは、業界を俯瞰的に見ることができる。
-かなり深い情報がまとまっているので、
【デメリット】
-業界誌は比較的価格が高く、入手が難しい。
-市況や、経営など情報の視点が高いことが多いので腹落ちさせることが難しい。
・企業が出している株主総会資料等
【メリット】
-ほとんどの場合、スライドが用意されているので分かりやすい。
-企業の経営陣から見た、業界や企業のことがまとまっているので採用においても使える情報が多い。
【デメリット】
-市況や、経営など情報の視点が高いことが多いので腹落ちさせることが難しい。
-企業から見た、市場感が書かれていることが多いので客観的な情報ではない可能性がある。
・その業界で働いている社会人
【メリット】
-実際に仕事をしているので業界、企業のリアルな情報が聞ける可能性がある。
-基本的に依頼すれば次の社会人を紹介してくれるので、深い理解が早くできる可能性が高い。
【デメリット】
-基本的に、大手企業は東京や大阪で働いている人がほとんどなので、地方から会いに行くのに時間とお金がかかる。
-同じ大学に先輩がいない場合には、実際に会うのが少し難しい。
・その業界に内定している先輩
【メリット】
-同じ大学の先輩などだと、会いにいきやすい。
-就活を経験しているので、実際の選考につながる情報が聞ける可能性がある。
【デメリット】
-まだ実際に働いたことがないので、情報が薄い可能性がある。
-基本的に1年前に業界研究をしているので最新の情報は別の方法で取得する必要がある。
基本的にはどの情報源も、メリット、デメリットがあるので、就活の段階や習熟度に合わせて、いろんな情報源を使い分けることをおすすめします。
まずは、業界研究用に情報がまとまっている書籍や、内定者の情報から入り、企業の公開している情報や、働いている社員に聞くようになっていくパターンが多いようです。
まずは自分の身近に業界のことを少しでも知っている人がいないか、探してみるのがよいかもしれませんね。

業界研究がそんなに必要ない人もいる?
ここまで、業界研究を行う目的や、行なうタイミング、実際の進め方などをまとめてきましたが、実は業界研究がそれほど必要ない就活生もいると思います。
特に、業界に対してのこだわりが、強くない学生にとっては業界研究はあまり意味がないことが多いです。
大きな裁量を持って働くことや、事業を創りたいなど、業界問わず就活の軸が決まっている場合には、業界研究よりも企業研究をより深く行った方がいいかもしれません。
業界研究について、先輩にインタビュー
ここまでは、就活における業界研究とは何かを整理してきました。次に就活を通して、業界研究を経験している先輩に、業界研究について聞いてみました。
今回お話を伺ったのは、今井さん(仮名)。今井さんは、旧帝大出身でコンサルティングファームの内定を得たとのこと。それではお話を伺っていきます。
業界研究は、差をつけるチャンス
-今井さん(以下、今井と記載)、本日はよろしくお願いいたします。
-コンサルティングファームへの内定、おめでとうございます!どのタイミングで、コンサルティングファームへ行くことを決めたのですか?
今井:ありがとうございます!コンサルティングファームの選考を受けようと決めたのは、3年生の5月ですね。
もともと、コンサルティングファームに入社したいと考えていました。
大学時代にビジネス領域の研究や、ビジネス系の学外活動において、コンサルティングファームが出すデータによく触れていたんですよね。そのときから、コンサルティングファームに興味を持ちました。
-なるほど、結構早くから興味はあったのですね。
今回の記事が業界研究の記事なのですが、業界研究はどのように進めていたのでしょうか。
今井:結構、いろんなものを調べましたね。まずはコンサルティングファームに行った、大学の先輩に話を聞きました。
ただ、先輩に聞いたくらいの情報だと就活を始めたころに持っていた、コンサルティングファームの印象からあまり変化することがなくて、理解が深まっている気がしなかったですね。
先輩からの話で、とてもありがたかったのはもう少し実際の選考に寄った話でしたね。
-就活開始当初はどんな印象を持っていたのですか?
今井:漠然と、経営課題の解決や、企業国からの依頼でリサーチ、政策提言をしていると思っていました。
-その後はどうやって、業界研究を進めたのでしょうか。
今井:実際に働いている方を紹介してもらって、会いにいっていましたね。あとはコンサルティングファームの名前が出るニュースを徹底的に読んでいました。
基本的にはWeb上の情報になるのですが、Googleアラートを使ったりして、毎日見るようにしていると実はデザイン系の企業を買収していたり、コンサルティングだけではなく、実務面が強い企業もあるなと分かったり。
実際に働いてる方からは、社風やどんなクライアントのどんな案件が多いのかなど、あまりオープンにならないような情報を聞いていましたね。
特定の業界に強いコンサルティングファームがあることなどは、社員の方からの情報で知りましたね。
-業界研究で気をつけていたポイントはありますか?
今井:複数の情報に触れることですかね。
業界研究って、専用の本だけで終わらせている就活生が多い気がします。グループ面接の時に、結構感じることが多かったです。
でもそれだと、採用担当の方も分かりますよね。他の就活生と同じだと思われてしまう。
結局は人気の業界であればあるほど、多くの就活生が選考を受けるので、周りよりも何らか目立つ必要があると思います。
それはこれまでの経験でも良いし、業界分析や企業分析の深さでもよいですが。
企業は、誰でもよい訳ではなくて、自社で活躍する人を採用したいと思っているはず。
そして、実は業界研究は、多くの就活生があまり力を入れないことなので、活躍できそうと感じてもらうチャンスな気がします。
そこまで情報を取りに行っているのかと。熱量も伝わりますしね。ぜひ、就活生にはいろんな情報を取りに行って欲しいなと思います。
-本日は、ありがとうございました。